V.A.『VANITY Music, Tapes&Demos』

V.A. 『VANITY DEMOS』
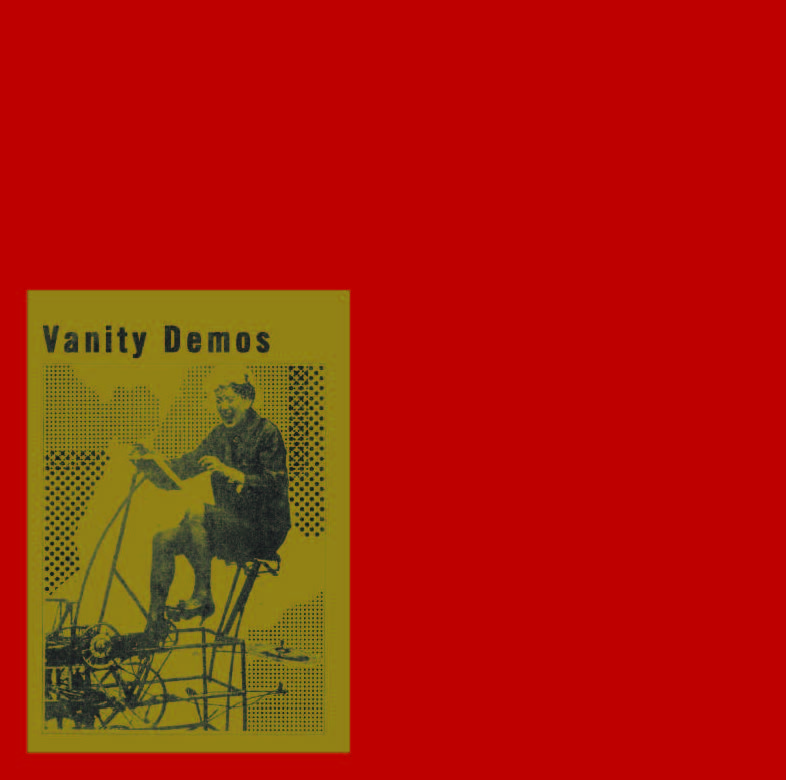
TOLERANCE『TOLERANCE』

『ロック・マガジン』とVanity Recordsと音楽的背景と当時のことなど
嘉ノ海幹彦(元ロック・マガジン編集/FMDJ)

2020年4月14日(故阿木譲の誕生日)に「きょうレコード」からremodelとしてそれぞれのコンセプトにふさわしい意匠を凝らした3BOXがリリースされた。特に『VANITY Music,Tapes&Demos』のCD-BOXは、1980年4月に創刊されたポータル・マガジン『fashion』01号のブックデザインを踏襲しており表象そのものが経年の色彩を纏って音楽作品として甦った。今回リリースされたこれらVanity Recordsの作品群は、世界同時的に発生したインディペンデント・レーベルと呼応し、霊的衝動と呼ぶべき情動の中で生み出された1980年代音楽シーンにおける時代精神の痕跡である。
ここでの時代精神とは、80年代の社会のなかで音楽が告げたオルタナティブな精神のことである。それは多様な表現へと分化していった精神的な生命運動のようなものだ。しかも音楽は時代の「気分」と深く関わり、それゆえに最も影響力が強いものである。
『ロック・マガジン』が行ってきたことは、音楽を通して時代を読み解く行為であり、強い内的要請に基づくものだった。換言すれば、時代精神が『ロック・マガジン』を生み出したということだ。そして今も自分の音楽体験の基本となっている。
それでは未発表音源の響きを聞きながら当時の背景などを記述しよう。
■Vanity Records設立の時代背景と阿木の想い
Vanity Recordsは、1976年の『ロック・マガジン』創刊から2年後の1978年に設立された。CD-BOX(Vanity Demos)に同封されたブックレットには2010年の阿木譲が自分自身の言葉でVanity Records設立を思い立った経緯とインディペンデント・レーベルの功罪について記載している。阿木は独立レーベルを想起するにあたり、イギリスの新興レーベルであったVirgin Recordsでリリースされる音楽に大いに刺激を受けていることが分かった。また阿木は、一部のインディペンデント・レーベルが商業主義的影響を受けオルタナティブな新しい音楽をリリースしなくなったのも同時に見ていた。
阿木はそのことを踏まえレコード産業の思惑に左右されないミュージシャン主体の新しい音楽をリリースするレーベルを作りたいと思い、Vanity Recordsを1978年に設立したのである。当時の『ロック・マガジン』に記載されているが設立には阿木の並々ならぬ想いが溢れている。(拙文Vanity Recordsと『ロック・マガジン』1978-1981参照)
また『ロック・マガジン』誌上でも紹介したが、イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、アメリカなどにおいてVanity Recordsと同様に自由で何の制約も受けない自らの意思で運営できる新興レーベルが同時多発的に誕生するのである。これらの動きにも時代霊が大きく作用しているとしか思えないのである。
またこれら新興レーベルの運営主体はミュージシャンやプロデューサーであり、商業主義から影響を受けないようなディストリビュートの仕組みを含めて設立されている。
ちなみにこの時代に設立された代表的なインディペンデント・レーベルを列挙してみた。
これらのレーベルが1980年代の時代精神を牽引したのだった。
1972年
Virgin Records
Ralph Records
Cramps Records
1975年
Obscure Records
Sky Records
1976年
Industrial Records
Los Angels Free Music Society
Stiff Records
1977年
Beggars Banquet Records
1978年
Vanity Records
Lovely Music
Recommended Records
ZE Records
Fetish Records
Factory Records
sordide sentimental
Small Wonder Records
ROUGH TRADE
Cherry Red Records
1979年
2Tone Records
COME ORGANISATION
United Dairies
Mute Records
4AD
Crass Records
Ata Tak Records
1980年
Zickzack Records
LES DISQUES DU CREPUSCULE
■『ロック・マガジン』とVanity Recordsの1980年代よりの展開
「1980年までは、81年からの80年代音楽を準備する期間だった。だから1980年はまだ70年代なんだよ。」阿木譲は音楽と時代性との関連を話題にしたときに、1970年代というのは71年から80年までのことで1981年からが本当の80年代が始まるのだとよく話していた。
そのとおり1980年は『ロック・マガジン』とVanity Recordsにとって大きな変化があった年だった。
81年に入ると「時代性」に特化した『fashion』も03号まで出版したが休刊とした。04号は特集「スーパーマーケット」の予定だった。
第二期『ロック・マガジン』最後の号である1980年11月発刊の特集エリック・サティ Funiture Musicのlast wordで阿木は要約すると以下のことを書いている。
1.1年前までのロックマガジンのバックナンバーを処分
2.千駄ヶ谷にあった東京事務所を閉じる
3.大阪の編集室を引越す
4.11月5日に『B.G.M』を、12月5日に『ノーマルブレイン』をリリース
5.年内(1980年)にはカセットテープからLP2枚組みの「ノイズ」というタイトルでリリース
※実際は『MUSIC』としてリリースされた
6.11月までにカセットテープの送付を呼びかけ
第三期の『ロック・マガジン』から東京事務所を閉じた関係もあり『遊』の広告は掲載されているが、工作舎とも疎遠になった。『ロック・マガジン』と関係のある出版社はなくなった。もとより音楽他誌には関心がなかったし書店で手に取ることもなかった。当時Throbbing GristleやCabaret Voltaireをまともに紹介しているメディアもなかったからだ。
時代に先駆けて出現しつつある新しい音楽を現前させるという使命感で『ロック・マガジン』は再スタートした。ライターにしても松岡正剛をはじめそれまで掲載されていた個人原稿もなくなっている。
言葉で説明できる世界が大きく変わろうとしていた。70年代から80年代へと。そして『ロック・マガジン』は80年代に音楽で時代を読み解く独自な方向性を色濃くするのである。
『ロック・マガジン』はまず版形がA4からB5サイズになった。特集ごとに内容から細かく紙見本や色見本より選択し編集した。ただ雑誌を作る際に紙質も色も毎号異なる組み合わせは、手仕事に近い作業となり、製版、印刷、裁断、製本に至るまで様々な影響が出た。各工程でそれなりの手間がかかるため業者からは嫌がられたが、今思うと結果的には「オブジェ・マガジン」といっていた雑誌『遊』の初期に近い。そしてこの手作り感のあるデザインはその後『EGO』や『E』へと引き継がれていく。
Vanity Recordsに関しても変化があった。『SYMPATHY NERVOUS/SYMPATHY NERVOUS』、『BGM/Back Ground Music』、『Ready Made/Normal Brain』を連続してリリース。リリース直後からVanity Recordsと『ロック・マガジン』の動きに触発された無名のアーティストの手によるカセットテープが全国から多数編集部に送られてきた。
そのことから『ロック・マガジン』と連動した「動き」となっていたことが分かる。この「動き」を受けてVanity Recordsでは、音に宿る時代の雰囲気をそのまま生かしマスタリングなどの処理を施さないかたちでリリースしようということになった。
音源が多種多様なカセットテープであり、ヒスノイズが内在する音という意味で、最初に付けられたアルバムタイトルは『ノイズ』だった。しかし結局阿木より「『ノイズ』ではなく、ずばり『音楽』にしよう。」ということになり『MUSIC』と名付けられた。時代を先取りしているものが、「音楽」であるという感覚が『ロック・マガジン』にはあったからだ。
「ロックはあらゆる要素を吸収するスポンジだ。」というブライアン・イーノの発言にも裏付けられている。ここでいう「ロック」とは、パンクでもロックンロールでもJAZZでもなく「音楽」のことである。つまり音楽が全ての世界現象(リアル)を水のように溶解し、スポンジのように吸収し保持し現前化(リアリティ)させるということであり、『MUSIC』を出すことで音楽とはまさにプラスティック・フォースを内在化した可塑性芸術であるということを示したかったのである。
そして『MUSIC』は阿木の「1980年末までが1970年代である」と言う考えに基づき1980年の12月にリリースされた。しかし募集の締め切りが過ぎたにも関わらず、その後もカセットテープが無名のミュージシャンから日々編集部宛に郵送され、第三期最初の『ロック・マガジン』01号 1981/01 特集 INDUSTRIAL MYSTERY MUSIC=工業神秘主義音楽の2ヶ月後の『ロック・マガジン』02号1981/03 特集WHITE APOCALYPSE FEMALE では、カセットテープ・ミュージシャンを特集することにした。「騒音仕掛けの箱に吹き込まれた風景」と題したセクションではカセットテープのレイアウトやデザインと共にP80-100まで21Pにわたって阿木と当時編集者であった明橋大二の対話形式により紹介されている。(VANITY Music,Tapes & Demosブックレットに掲載)
Vanity Recordsではそれら様々なミュージシャンを『MUSIC Ⅱ』、『MUSIC Ⅲ』のように連続する作品としてリリースすることも考えたが、LPでのリリースとはならなかった。理由は、時代の変化に追いつくよう、スピードを重視したからだった。
しかし一方でひとつの試みとしてVanity Recordsのリリースとは別にソノシートを利用することを考えた。それまでソノシートは『ロック・マガジン』の特集を強調するための補足的な意味で「おまけ」として添付していた。
カセットテープ・リリースの時に試みたと同様に、『ロック・マガジン』の読者参加でバンドをピックアップした。『ロック・マガジン』のレコードコンサートに参加したり、編集部へ遊びに来たり翻訳を手伝ったりしていた青木寶生の『ほぶらきん』や佐用暁子の今回CDリリースされた『Love Song/System』がこのケースに該当する。『ロック・マガジン』誌編集行為の一環といってもいいだろう。
またこの時期、Vanity RecordsのLPとしては最後の作品となる『TOLERANCE/DIVIN』がリリースされた。
その後もっと簡易にもっと容易にもっと安価にもっとシンプルにリリースできるものとして、後期のVanity Recordsではカセットテープでのリリースという形態をとった。
当時の時代背景としては、都市生活者が遊民になり快適に過ごすためのツールとしてのカセットテープ文化が一般的になりつつあることにあった。既に1979年にソニーより「音楽を持ち歩く」というコンセプトの元にウォークマンが発売され、都市機能の一部を有していた。その後1981年には細川周平の『ウォークマンの修辞学』(朝日出版社 エピステーメー叢書)が出版されている。
遊民(フラヌール)とはヴァルター・ベンヤミンがボードレール論を展開する中で使用している概念である。市民社会が形成される歴史的背景の中で民衆は定住の場所を持たず都市の街路の中で遊民化する。ベンヤミンは遊民のことを次のように説明している。「エドガー・アラン・ポーの<群集の人>はいわば探偵小説のレントゲン写真である。そこにあるのはその備品、すなわち追跡者、群集、ロンドン市内をたえずその中心から離れないようにしながらうろつく見知らぬ老人だけである。この見知らぬ老人が遊民である。」
また1981年にはレコードから、手軽にリリースできるカセットテープへと変化していった。アンダーグラウンド・シーンでは国内外を問わずカセットテープでのリリースが始まっていた。
次にハードウエアについてもカセットテープのダビング機能が付加されたダブルカセットデッキへと技術的進歩は続き、音楽制作とダビングによるリリースを身近なものとした。このような時代へのアプローチ、リリースの速度感覚、デザイン感覚などの綜合が『VANIY TAPES』として結実する。
前述の『ロック・マガジン』02号では「SALARIED MAN CLUB」「KIIRO RADICAL」「DEN SEI KWAN」「INVIVO」「WIRELESS SIGHT」「NISHIMURA ALIMOTI」など多くのカセットテープを送ってきたミュージシャンが紹介されている。Vanity Recordsでは、時代の風景としての騒音群という意味を込めて『ノイズ・ボックス』と名付けられてセットリリースされた。後に『VANIY TAPES』としてリリースされるものである。『ノイズ・ボックス』の中には「私の耳は貝の殻 海の響きをなつかしむ」というジャン・コクトーの言葉がカードにされ同封されていた。
また羽田明子が送ってきたレ・ディスク・ドゥ・クレプスキュールよりリリースされたカセットテープ『From Brussels with Love』が紹介されている。内容はジョン・フォックス、ドゥルッティ・コラム、デア・プランの音楽の他にブライアン・イーノやジャンヌ・モローのインタビュー(声)も含まれている。
———————————————————–
■V.A.『Vanity Demos』
それではBOXに格納された作品を紐解いていこう。

Vanity 8102『Love Song/System』
『ロック・マガジン』02号 1981/03 特集WHITE APOCALYPSE FEMALEの付録としてリリースされた。『ロック・マガジン』では世紀末特集としてWHITEHOUSE(ウィリアム・ベネットが1979年に設立したCOME ORGANISATIONからリリース)を全面的に紹介。同じく1979年に設立されBAUHAUS LEWIS&GILBERTなどをリリースしていた4ADレーベルを紹介している。また同じく1979年のCrass Recordsも紹介。Nurse with Woundのスティーヴン・ステイプルトン設立のUnited Dairiesも1979年だ。
「SYSTEM」は佐用暁子のバンド。メンバーは沢田弥寿子、大前裕美子、初田知子、芦田哉女の5人。『ロック・マガジン』01号 1981/01のP88-89に紹介されているが、文字通り、パフォーマンス的感性を身体化させているバンドだ。メンバーに翻訳のお願いをした記憶がある。それだけ『ロック・マガジン』との繋がりが強かったバンドといえる。
「SYSTEM」について阿木はアントサリーと違ってパフォーマンスの必然性を持っていないと語っていた。しかし彼女たちは時代のスタイルに合わせてその中で踊っているだけだ。楽しむための音楽、だから「Love Song」。「SYSTEM」は5人の情念的な織物のようだ。歌詞を紹介しておく。
「Love Song」
あなたの血管が動く/空気が動く/ねえ、地球っていつまでもつと思う?
あなたの心臓きこえる/時間がきこえる/ねえ、地球っていつまでもつと思う?
大きく口を開けてみて/私が手を突っ込むわ/あなたの心臓をつかんで/吹き出す夢、リズムの連続
あなたの血管が動く/あわせて私は踊る/あなたの心臓の音/あわせて私は踊る
空気が動く、時間が動く/私が動く、あなたが動く/記録する夢、リズムの反復/ねえ、地球っていつまでもつと思う?
———————-

Vanity 2005『Today’s Thrill/Tolerance』
『ロック・マガジン』2006号 1980/07 特集ATTERNATIVE MUSICの付録としてリリースされた。Toleranceが一番進化した頃の音源であり既にエレクトロニクスの特性を発見していた音楽。歌ではなく声の中の響きと電子音の響きが同じものであると感じさせる。響きのコンクレート(具体)化はエロティシズムへの昇華する。ワクワクする快感とぞくぞくする恐怖は同義語であること理解させる。『ロック・マガジン』では「トレーランスは感性機械だ。論理ではない、運動力学とエロスが合体したものだ。」と表現した。まさしくリゾーム的音楽である。
Tolerance丹下順子が『ロック・マガジン』でのインタビューにこのように語っていた。
「私にとって音楽ってのは、言葉とか考えだけで言うと、文学ってのは本だけで終わりだけど音っていうのは生活として重要だし、食事をするとか眠るとかと同じレベルで私の中で重要です。」
サイコロの1から6以外の目が次々に出てくるような興奮を憶える。それはToleranceを意味する寛容/受容の差異が生み出す震えるような感覚である。
———————-

『VA/Demos』
今回のBOXセットのために提供された1981年当時に作られた未発表の音源集。この中に痕跡/意味を見出すことを試みる。非常に『ロック・マガジン』的な特徴を持ち無機質な物語の短編集のようなアルバム。工業神秘主義音楽であり、繰り返しの中に時代を逆なでする響きが潜んでいる。
リズムは感性のダンスミュージック。1980年代にこんな音楽を作っていたのかと驚いた。これら工業神秘主義音楽群は時代を予感するイメージを次々と提示してくれる。
収録されたのは、SALARIED MAN CLUB、ONNYK:Anode/Cathode(陽極/陰極、電解槽・電子管)、DEN SEI KWAN(電精館)の3アーティスト。
・SALARIED MAN CLUB
『ロック・マガジン』03号 1981/05特集DANCE – MACHINEの誌面でSALARIED MAN MANIFESTを掲載している。ここでは都市生活者の欲望と情報、消費と変容が記載されている。少し引用してみよう。「人間は、この世界の終わるまで、あらゆる物質を創造し、流通させ、消費する。そして、その回転をますます速めていくだろう。」
これは1981年に書かれたが、やがて自滅するであろう資本主義社会を、自覚的に崩壊させようとする加速主義のファクターを告げた宣言とも読めなくはない。
1.Perspective
遠近(画)法、透視画法、遠近図、遠景の見通し、眺望、前途、将来の見通し
2.Close My Eye
瞳をとじて
3.Intellctual Mirror
知性のすぐれた、理知的な、鏡
4.Epilogu
Epilogue 終章、終曲、または物事の結末 ⇔ プロローグ
・ONNYK
ONNYKこと金野吉晃の音楽は、ブライアン・イーノがプロデュースした「NO NEW YORK」(1978年)にクレジットされているザ・コントーションズのジェイムス・チャンスを彷彿とさせる。ただのファンクだけでなく、パンクとインダストリアルとテクノと即興と時代が加算されている音楽。
『ロック・マガジン』01号 1981/01 特集 INDUSTRIAL MYSTERY MUSIC=工業神秘主義音楽の誌面では、『Music』に参加したミュージシャン達の言葉とイメージをそのまま掲載した。その中で金野吉晃は「Anode/Cathode」名義での「-..Of The Passive Voice Through The Light 光を通しての受動態の・・・・・」について以下の文章を寄せている。
「『我々は《音楽》を聴き得ない、我々が聞くのは《音楽》の影である』とはロナルド・ザースの言葉であるが。我々が粗末な聴覚器を通じて、何の脈略もない空気振動に幻を見る(?)のは勝手であり、許された暴力だ。何も今更こんな事をいう必要もないのだが、この利用価値のない単なる磁束線密度の変化パターンは、磨滅しながらも拡散しつづけ、何の「イメージの裏うち」もないところである時突然に逆転され、回路を断たれる。つまりテープはそこで切れてしまうのだ。《音》は我々を記憶してくれないだろう。「見る」のを見ることはできない。では、「聴く」のを聴くことは・・・・・・?」
5.Talk in the Dark
暗がりでの会話
6.Homage to the Luminous Animal living in a Far an…..
敬意、尊敬 発光動物 遠くに住んでいる
7.My Stygma
汚名、恥辱
・ONNYK SOLO
8.Onnyk self trio
・TOZAWA+ONNYK
9.TOZAWA+ONNYK
・EXCEPT FROM HMN SESSION
10.Homemade Nosie X
・DEN SEI KWAN
11.Last
電精館1979年か1980年の作品。
遠方からイギリス人作曲家コーネリアス・カーデューのピアノ曲「アイルランドおよびその他の作品に関する4つの原則」のアイルランド民謡が幽かに聞えるが、弱い電磁気力でかき消されていく。聴き終わったら痕跡だけが残った。残った音は宇宙の縁にでも張り付くんだろうか。
———————-

DEN SEI KWAN P’ remodel 19
『ロック・マガジン』02号 1981/03の評を受け1981-1982年に作成された。完成度が高くこのままToleranceの次にVanity RecordsLP13枚目の作品としてリリースしたかもしれない。
DOME的で工業神秘主義音楽の系譜の音楽だ。亡霊の聞えるはずのない声のようなリズムに内在する轣轆(車の軋み)。DOME(ドーム)とは天蓋の意味であり、古くからある平行宇宙説で語られる天蓋のことだ。地上界と天界は写し鏡となり結び付いた因縁を持つとされた。しかしながら天蓋に描かれた星辰も地上的な投影でしかない。この地上的な投影から天球儀が生まれて来た。カールハインツ・シュトックハウゼンは晩年最後の来日の際に、究極の音楽は完全な球形の中で平等にあらゆる方向から響く空間で体験することであると語っている。そして作品「リヒト・ビルダー(光=イメージ)」をそのような空間芸術として夢想していたのかも知れない。
DEN SEI KWANの天蓋音響もこのような体験が可能だろう。だからこの音楽には懐かしさや郷愁(ノスタルギア)みたいなものを感じる。前世に遠いどこかの惑星にいて聴いていたような音楽。
———————-

Tolerance DOSE remodel 25
Toleranceは感性機械が奏でる言葉の音響としての織物だ。過去の空虚な亡霊の眠りを伴って、有毛運動の長い響きは幽かに渦巻きのような回転を繰り返す。
このアルバムは機械の中の異世界に誘われる心地よさがある。この時代の文字通りプログレッシヴ・ロックなのだ。
DOSEとは投薬/服用であり受動/能動の関係である。またToleranceは別に依存症薬物が効かなくなる耐性を意味する。まるで人間が存在しなくなった世界(地球)の映画館で上映される映画音楽、または壁紙と化してしまったタブローのようである。
———————-

Tolerance DEMO remodel 26
天蓋に木霊するハルモニアの音楽のようだ。電子音と人間との合体。柔らかな水の中で手で触れられる耳毛細胞を振動させ電流を通して音のパルスを発信し続ける。
当時丹下順子はクラフトワークが好きだった。そして好きな理由は機械と人間との合体だといっていた。自分が機械に同化したサイボーグの内なる器官を感じながらエレクトロニクスと接していたのだろう。
しかしこの後なぜ封印してしまったのだろう。感性機械はもう動かないのだろうか。
否!今も彼女の生活の中で密かな拍動と共に響いているのだろう。
でもこのような音楽を聴いたら、これはこれで美しい。
**************************************
