嘉ノ海幹彦が関わった編集物リスト
■『fashion』について
『fashion』は音楽とは一線を引いた商品の表象としてのポータルマガジンとして発刊された。阿木は『ロック・マガジン』2004号で定期的に本を出すと宣言している。その段階では誌名は「ポップ」と考えられていた。しかし誌名が『fashion』になったのは、「ファッションは生活の中で、時代毎の世界観と宇宙観の反映であり、建築、芸術、モード、産業、そして音楽にいたるまでくまなく反映されるものだ。ファッションはひとつひとつ掘り下げて時代の読み解きを行う」というコンセプトによる。
レイアウトや装丁は阿木が行った。楽しそうに本というオモチャ箱を遊んでいる感じだった。細かい部分でのデザインセンスが光る。

fashion 1 1980/04 特集1960’s
1960年代の精神の系譜を特集。60年代の商品を中心とした生活スタイル、モッズ、消費社会としての文化を掘り下げ時代そのものを再評価することを目的として編集された。当時のモッズシーンについて羽田明子の取材記事が掲載されている。60年代の時代精神は一体何を残したのか。
なお『VANITY Music,Tapes&Demos』の意匠はこの号のブックデザインを踏襲している。

fashion 2 1980/06 特集Plastic
「私は、可塑性である/強靭である/軽量である/断熱性である/曲線的である/電気絶縁性である/重合する/流れる/全てのプラスティック・ピープルよ!「重合」し、「流れ」、「変態」せよ!! 」から始まる巻頭のプラスチック宣言では、性質の可塑性に注目し様々な要素を容体化させるプラスティック・フォースの現われを分子構造から生活用品まで展開している。「変容」を追求したゲーテ形態学との関連で「プラスチックの源流はゲーテである」と語る松岡正剛やプラスティック・ピープル、人口臓器メーカー、美容整形医師などへのインタビューも掲載した。本誌左下に仕掛けられたパラパラ動画のミスター・スポックがcontinuous photography(連続写真)により服を脱いだり着たりする。

fashion 3 1980/08 特集MACHINE
1968年にニューヨーク近代美術館で開催された「機械(MACHINE)….機械時代の終わりに」展についてのポントゥス・フルテンの翻訳である。レオナルド・ダ・ビンチから大阪万博のペプシ館のE.A.T.(Experiments in Art & Technology)グループまで記載した書物だ。MACHINE=機械というものを中心にそれに纏わる精神技術史といってよい。もちろんマルセル・デュシャンやジャン・ティンゲリーやナム・ジュン・パイクも紹介されている。ジャン・ティンゲリーの音響装置は、フランツ・カフカの『流刑地にて』の殺人機械や後のマイク・ポーリンのサバイバル・リサーチ・ラボラトリーを連想させる。
—————————————————————-
■1980-1981の『ロック・マガジン』について
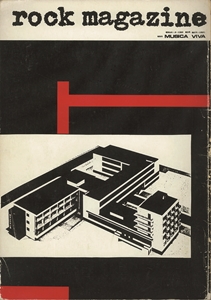
『ロック・マガジン』2003号 1980/01 特集 MUSICA VIVA
戦後電子音楽スタジオが国を上げて開設されるが、特にドイツ、日本、イタリアなどの敗戦国ではすぐに取り掛かり、MUSICA VIVAの作曲家が活躍することになる。電子音楽はミュージックセリエリスムに応用され音の響きを重視した音楽へと変貌する。「耳は聴かない。聴くのは知性だ」とはMUSICA VIVAの作曲家で確率論を音楽に導入したヤニス・クセナキスの言葉だが、音楽を体験するためのヒントを与えてくれる。
さて、ここで少しこの特集号にまつわる当時の状況とこの本の必然性について述べたいと思う。MUSICA VIVA特集が出版された1980年という年は、70年代後半よりニューヨークに端を発したパンク・ムーブメントがイギリスで商業化されセックスピストルズに象徴されるようなロックミュージックに展開している時代であり、もう一方でROUGH TRADEのような反商業主義的な動きの中にあった。後者からはザ・ポップ・グループやスリッツ、キャバレー・ボルテール、スロッビング・グリッスルなどが出現し、日本ではミラーズ、ミスター・カイト、フリクション、SKENなどの東京ロッカーズやSS、アントサリー、イヌ、ウルトラ・ビデなどの関西NO WAVEと呼ばれたグループが活動していた時代でもある。
そしてイギリスのファクトリー・レーベルから出ていたジョイディビジョンのボーカリスト、イアン・カーティスの死によって決定的な相違が80年を境に出現してくる。先に上げたスロッビング・グリッスル達は歌詞を持たないミュージシャンであり、表現主義的なジョイディビジョンの終焉と共にインダストリアル・ミュージックとクラブ・ミュージックが出現してくるのである。言葉を持たない音楽は言葉以上に語りだすのである。

『ロック・マガジン』2005号 1980/05 特集 ROUGH TRADE
自らの手で自らの音楽を作り上げるシステムとしてイギリスの独立レーベルROUGH TRADEと呼応するように、阿木は「ソニック・デザイナーと呼ばれる新しい姿勢を持ったアーティストたち」を記載している。
「RNA ORGANISM」「Normal Brain」「SYMPATHY NERVOUS」をソニック・デザイナーと評している。「総てのハードウエアを自分のものにし、機械を自身の中枢神経の延長線上のシステムととらえ、音をデザインすること」をソニック・デザイナーと定義する。これは、『ロック・マガジン』次号の「日本のハイ・テック・マシーン達」への前哨であり、Vanity Recordsが果たす新たな役割を模索している。

『ロック・マガジン』2006号 1980/07 特集 Alternative Music
「cabaret voltaire」、「the pop group」と同等に「tolelance」、「rna・o」、「sympathy nervous」の名前が表紙に記載されている。「魚の側線のような触覚を持った、テクノ・ポップ以降に現れた日本のハイ・テック・マシーン達」と題してP8-15に8ページにわたってVanity Recordsのミュージシャンが紹介されている。「Mad Tea Party」と「Perfect Mother」をシングルリリースしたミュージシャンも加えて彼らが自らの言葉で自らの創作する音楽について語っている。

『ロック・マガジン』2007号 1980/09 特集 sordide sentimental
2006号と同様に「Throbbing Gristle」、「Joy Division」と「b・g・m」、「normal brain」の名前が表紙に記載されている。
『sordide sentimental』はジャン・ピエール・ターメルにより1978年にフランスで創刊された7inchレコードが添えられている書物だ。『ロック・マガジン』と同様にデザインと言語により音楽を通して時代を読み取るための思想を持つ雑誌であり、既に「Throbbing Gristle」、「Joy Division」などをリリースしていた。『sordide sentimental』と呼応するために急遽特集を組んだ号である。
また1979年設立のmute recordsや1978年設立のfactory recordsのその後展開される様子が羽田明子の取材を交えて掲載されている。「TAPE RECORDED DIALOGUE」とタイトルが付いた記事では、Vanity Recordsのミュージシャン達である「tolelance」、「b・g・m」、「sympathy nervous」、「normal brain」が参加してP82-87に6ページにわたり座談会形式でエレクトロニクス機器と感覚や感性について話している。

『ロック・マガジン』2008号 1980/11 特集 Erik Satie Furniture Music
「家具の音楽」とは元々エリック・サティが「家具のように、そこにあっても日常生活を邪魔しない音楽、意識的に聴かれることのない音楽」をコンセプトとして作曲されたものだ。ジョン・ケージがその考えを引き継ぎ「4分33秒」を作曲しブライアン・イーノが「Ambient Music」へと昇華した。Vanity Recordsの『BGM/Back Ground Music』(1980/09)も「家具の音楽」の系譜に位置される。特集ではサティの音楽を中心にベル・エポック時代の芸術と現代のロックを結び付けようとした。サティはグレゴリオ聖歌に代表される教会旋法を二十世紀に蘇えらせ神秘主義的教会音楽を多く作曲したが、スロッビング・グリッスルやキャバレー・ボルテールなどの音楽も同列に編集し、そしてサティの音楽や思想と1980年代に誕生したオルタナティヴな工業神秘主義音楽などを連続性を持って享受するための準備を行ったのである。

『ロック・マガジン』01号 1981/01 特集 INDUSTRIAL MYSTERY MUSIC=工業神秘主義音楽
2020年に亡くなったジェネシス・P・オリッジが「industrial music for industrial people」として展開したindustrial musicを工業神秘主義音楽と名付けた。紙面ではダンスミュージックと同時に音声詩、ダンス、シャーマニズムなどを同時に掲載。この号では以前からロシア構成主義やドイツ表現主義を生んだ時代の衝動について話を聞きたかった方々へのインタビューも平行して実施した。ロックではギャバレー・ヴォルテールやバウハウスが登場しアダム&ジ・アンツが「未来派宣言」を歌っていた。生まれたてのロックミュージックに20世紀初頭の未来派の精神が甦る。池田浩士はドイツ文学者でファシズムと大衆文学を研究している。また表現主義やフランツ・カフカを教養小説(人が体験を通して社会=時代の中で内面的に成長していく過程を描く小説)の文脈で読み解く人でもある。松岡正剛は「音楽の呪術的要素」と「第三商品論」を語った。土居美夫はスイスのチューリッヒで1916年に開店したキャバレー・ヴォルテールの店主でありボール紙の司祭フーゴ・バルの研究者である。バルの「時代からの逃走」を翻訳しただけではなくワシリー・カンディンスキーやパウル・クレーの研究者でもあるのだ。イギリスのシェフェールドのバンド、キャバレー・ヴォルテールやバルの音声詩「Gadji beri bimba」をロックにしたトーキングヘッズの「I Zimbra」の感想も聞いた。土居はバルがチューリッヒ・ダダの拠点となったキャバレーボルテールを閉店した後「キリスト教神秘主義」の研究をしていたと資料とともに教えてくれた。黄寅秀はヤンハインツ・ヤーンの『アフリカの魂を求めて』の翻訳者であり在日の韓国人。アフリカでは元々音楽は哲学であり医療でもありシャーマニズムの源泉でもあった。アフリカ人の移住に伴いその土地の音楽と融合し変化し新たな様式を生み出した。世界に広がった音楽そのものの有用性について聞いた。またこの号から版形も紙もレイアウトも全く変わった。阿木が表紙の片隅に、溺れた友人を助けようとして自らも溺死したドイツ表現主義の詩人ゲオルク・ハイム(1887-1912)の詩を余ったインレタを使ってローマ字で記載している。阿木流の編集である。
ここに全文を掲載したい、忘れ去られた幻視者(詩人)の声を。
ぼくらの病気は、ぼくらの仮面である。
ぼくらの病気は、際限のない退屈である。
ぼくらの病気は、怠惰と永劫の不休のエキスのようなものである。
ぼくらの病気は、貧困である。
ぼくらの病気は、ひとつの場所に縛りつけられていることである。
ぼくらの病気は、ひとりではいられないことである。
ぼくらの病気は、いかなる天職ももなたいことであり、もしなにか天職をもっているとすれば、その天職をもっていることである。
ぼくらの病気は、ぼくらにたいする、他人にたいする、知識にたいする、芸術にたいする不信である。
ぼくらの病気は、真剣さの欠如であり、いつわりの陽気さであり、二重の苦悶である。だれかがぼくらに言った、きみたちはそんなにおかしそうに笑っているではないかと。
この笑いがぼくらの地獄の反映であることをその人が知ってくれればいいのに。ボードレールの「賢者はただ身を震わせて笑うばかり」のにがい反対であることを。
ぼくらの病気は、ぼくらがぼくら自身に定めた神にたいする不服従である。
ぼくらの病気は、言いたいことの反対のことを言うことである。ぼくらは、聞き手の表情にあらわれる印象を見つめながら、われとわが身を苦しめざるをえない。
ぼくらの病気は、沈黙の敵になっていることである。
ぼくらの病気は、世界の日の終末に、その腐臭に耐えられぬほどに息苦しい夕ぐれに生きていることである。
興奮、偉大さ、ヒロイズム。以前はこの世界は時おりこれらの神々の影を地平線のあたりに見た。今日ではこれらは劇場の人形にすぎない。戦争はこの世界から出て逝ってしまった。永遠の平和が戦争をあわれに埋葬したのだ。
かつてぼくらは、こんな夢を見た。ぼくらはある名付けようのない、ぼくら自身も知らない罪を犯したのであった。ぼくらはある悪魔的な仕方で処刑されることになっていた。
ぼくらの眼のなかにコルク栓抜きをねじこもうというのであった。しかし、ぼくらにはどうやらまだ逃げだすことができた。
そして、ぼくらは――心に途方もない悲しみをいだきながら――むら雲の陰鬱な区画のなかをかぎりなく通っていく秋の並木道を、かなたへと逃げていくのであった。
この夢はぼくらの象徴ではなかったろうか?
ぼくらの病気。ひょっとするとなにものかがそれを治せるかもしれない。たとえば愛が。しかし、ぼくらはあまりにも重い病気にかかっているので愛でさえもできなくなっていることを、ついには認めざるをえないのであろう。
しかし、なにかがある。それこそぼくらの健康というものだ。三たび「それにもかかわらず敢えてなお」と言うこと、古参兵のように三たび手につばをつけること。
そしてそれから、西風に駆られる雲のように、ぼくらは街路を抜けて遠く、未知なるものへ向かっていくことだ。
「戯画」1911年6月19日 ゲオルク・ハイム 本郷義武訳

『ロック・マガジン』05号 1981/09 特集 SUR-FASCISM
ジョルジュ・バタイユの「コントルアタック」の時代とノイエ・ドイチェ・ヴェレを中心とした最先端の音楽を同紙面に掲載した。パリの「社会学研究所」コレージュ・ド・ソシオロジーとDAFの2拍子と強制収容所の音楽とジョルジュ・バタイユ、知らぜらる快楽主義者ピエール・クロソフスキー、ヴァルター・ベンヤミン、ロジェ・カイヨワなど。それらを「シュル-ファシズム宣言」として掲載した。
シュル-ファシズム(SUR-FASCISM)は、ヨーロッパ全土をパンデミックに席巻しはじめたファシズムに、哲学者であり作家のジョルジュ・バタイユや芸術家のアンドレ・ブルトンをはじめとした知識人や芸術家がファシズムの狂気を超える「狂気の超現実主義的ファシズム」(=シュル・ファシズム)で闘いを挑んだ。「コントルアタック」とは、この生死を賭けた芸術家のレジスタンスの名称のことである。西洋は、かつて経験のした事のない時代に突入した。強制収容所は現実化し、終末を歌わしてはくれない。
シュル-ファシズムと併せて音楽では、デア・プラン、DAF、ディー・クルップス、ヴィルトシャフツヴンダー、マラリア、アブヴェルツ、パレ・シャウンブルク、ディー・レミング、ソラックス・バッハ、ザオ・セフチェック、リーフェンシュタール、タンク・オブ・ダンツィッヒ、サイキックTV、ルイス・アンド・ギルバート、PIL、キリング・ジョークなどを紹介した。
************************************************************
※ 文中敬称略
最後になりましたが、この文章を書くにあたり、機会を与えて頂いたスタジオワープの中村泰之さん、内容についてのアドバイスと校訂を担当してくださった能勢伊勢雄さんに
