VANITY INTERVIEW ⑥ R.N.A. Organism (佐藤薫)
インタビュアー 嘉ノ海 幹彦
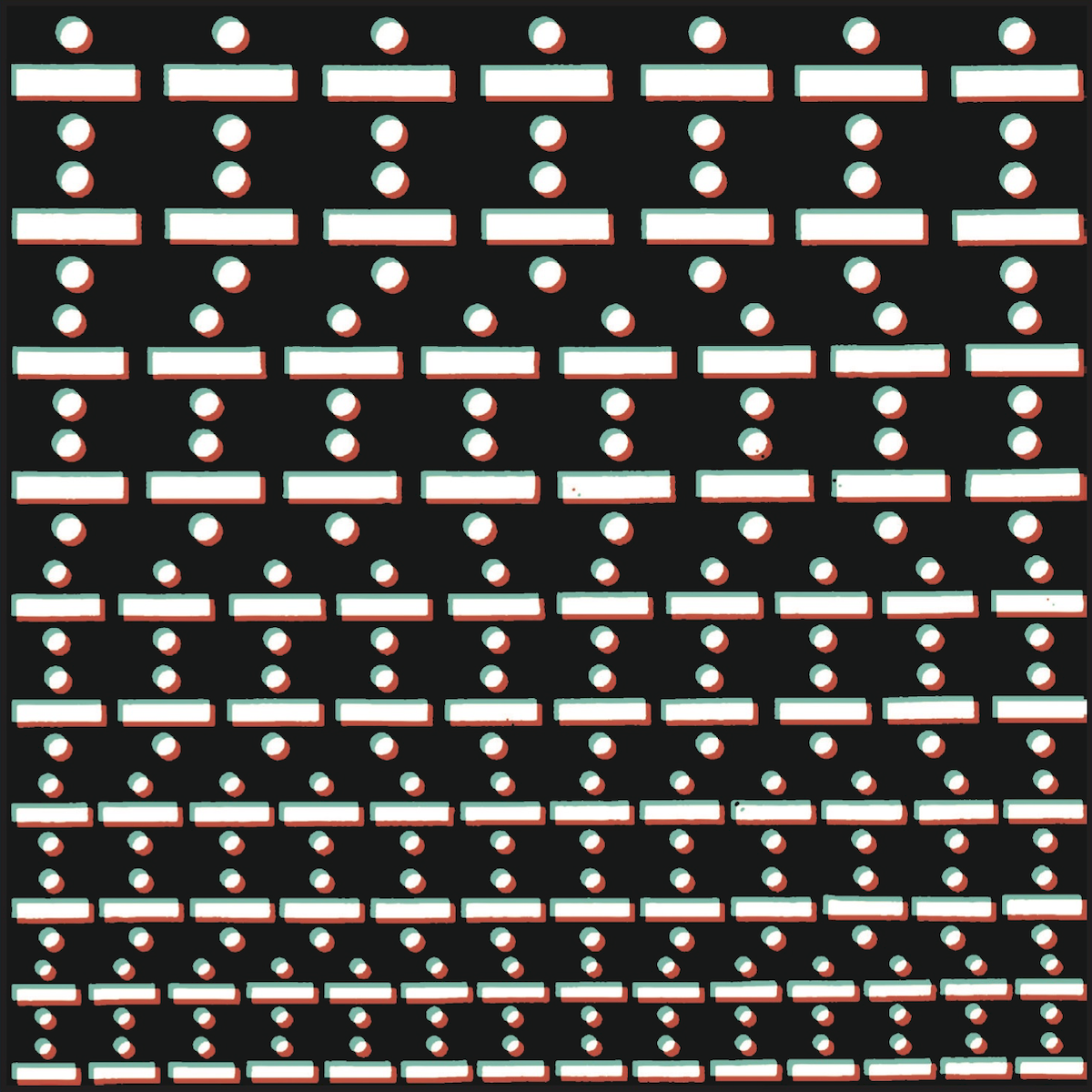
『内なるウイルスが交感する場所』
今回はR.N.A. Organismのプロデューサー、佐藤薫。当時、京都河原町「クラブ・モダーン」のプロデュースや東京のアート集団「イーレム」との共同作業やバンド活動など音楽制作のみならず様々な活動を牽引。そして現在では、φononレーベルのプロデューサーとして内外で活動されている。佐藤さんとはじめて会話したのは1980年の大阪四ツ橋にあったカフェ「パームス」だった。この年は『fashion』を発刊し隔月刊の『ロック・マガジン』と並行していたので毎月締め切りに追われ、日々の作業で忙殺されていた。Vanityについても同様で、この年にLP7枚と全タイトルの半数以上がリリースされている。だから『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』リリースの経緯は全く知らなかった。今回、そのあたりを中心に聞きたいと思っている。
==========================================
佐藤薫のプロデュースするφononレーベルへはこちらのサイトにアクセスして頂きたい。
レーベル・サイト:https://skatingpears.com/
試聴サイト:https://audiomack.com/sp4non
それではインタビューを始めよう。

●Vanity Recordsの中でもこの『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』という作品は、リリースの方法が他と比べかなり異質だと思ってます。まずR.N.A. Organismは国籍も含めて匿名のミュージシャンであり、最初に物語を創ってその具体物としてアルバムをリリースしました。阿木さんが『ロック・マガジン』2005 1980年5月号の中で「ロンドンはケンジントン郵便局の消印がある茶封筒にリリースして欲しいという英文と共にカセットテープが入っていた」(要約)と書いています。この文章がR.N.A. Organismという名前が公になった一番最初ですね。
まずVanityからリリースされた経緯はどのようなものだったのでしょうか?
また阿木さんとの初対面の印象はどうでしたか?
★正直はっきり覚えていない。70年代後半、ぼくは個人輸入したレコードを大阪のディスコなどに手売りしていたのですが、その頃なにかの機会にお会いしたのかと。78年頃から「パームス」というディスコ&カフェでぼくは週一のDJをしていて、確か阿木さんも同店で時々DJをしていたから、よく顔を合わせてはいました。だから初対面の印象は特にないですね。
とにかく阿木さんは、DJスタイルで音を聴けて踊れるようなクラブ的拠点となる、今様に言うとヴェニュー(Venue)がほしくて仕方ない様子でしたね。彼はその方面にはまったく疎かったので、ディスコ/ライヴ・ハウス/クラブ──などの流れなどについて話した記憶があります。
●まさしく「クラブ・モダーン」じゃないですか(笑)。たしか1980年からですよね。直接的には関係ないかも知れないけど、すこし「場所」との関連で話を聞いてもいいですか?京都河原町にあった「クラブ・モダーン」に何回か行きましたが、「場所」として特異なコンセプトを持っていたと思います。僕は昔から民族音楽が好きなのですが、ダンスフロアでは”THE POP GROUP”と同レベルでアフリカの民族音楽(そのまま)がかかっていて、お客さんは踊っていました。その時は時代の『ロック・マガジン』的展開だと勝手に思っていたのですけど(笑)。「場所」という現場から関係性を通して「モノ=形」が生まれてくるわけですから。
佐藤さんにとって「場所」とR.N.A. Organismとはどのような関連性というか位置づけにあったのでしょうか?
また、今の時代に必要なVenueとは何でしょうか?当時のVenueに変わるものでもいいです。
★ぼくがヴァイナル抱えてDJ周りをしていたのは「クラブ・モダーン」よりずっと前、関西では1973年からで、それ以前は東京の六本木あたりの箱で回していました。当時は主にブラック/ソウル/R&B・ミュージックを中心に選曲していたのですが、75年くらいにはディスコでディスコ・ミューシックを回すことに辟易していて、時間を区切ってクラフトワークやフェラ・クティ、カンなどをかけ始めたんです。そこにピストルズが登場したことで、「Autobahn」「Zombie」「Upside Down」「Flow Motion」「Anarchy in the UK ~ Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols」──あたりが入り乱れた混沌が一部のディスコに音連れたわけです。
そしてぼくが回してる箱では、ニューウェイヴ全般を踊れる踊れないを無視した形で無理矢理聴かされるようになっていったのですが、当然そのまま受け入れられるわけもなく数年間の紆余曲折の末、一般のディスコではかからないような曲だけがかかる所謂ニューウェイヴ・ディスコとして「クラブ・モダーン」に収斂していった感じです。そこに新たに加わっていた大きな要素は、ギグれるクラブ。DJで踊れるだけじゃなく小規模なライヴもできるようにしたことかな……。
ということで、ぼくにとっては「時代の『ロック・マガジン』的展開」というのはまったく逆で、こういう「場所(ヴェニュー)」が圧倒的に重要だということを阿木さんには力説しましたよ。彼はパームスを発展させることができれば……と考えていたようですが、ぼくは文化が違うからそれは無理だろうと。ディスコ文化ともライヴハウス文化とも異なる、どちらかと言えばサロン/カフェ的な方向の手頃な箱が必要だと……。だから「ロック・マガジンのヴェニュー的展開」がテーマだったはずですね。その後の阿木さんの馳駆の労を振り返れば明かですよね。
R.N.A. Organismに関しては、そのヴェニューに直結した位置づけはありません。なにしろ、ライヴにはメンバーは出演しないでカセットテープを送りつけてプレイしてもらうというスタイルだったので……。後にイーレムでまとめることになるバンドやユニットがいくつかあって、その中のひとつということです。彼らがライヴやイベントを開催する際の「場所」をモダーンのほかにも開拓していくことが重要でした。その際のポイントとなったのが、イス無しのスタンディングでギグれるスペースであることでした。今じゃ当たり前ですが、当時のライヴハウスなどは基本イスとテーブルは必須でしたから。その先鋒に立ったのが80年に結成したEP-4で、当初からスタンディング不可の場所では演らないと決めていて難儀しました。だから出演先ヴェニューとして多かったのが大学などのホールでしたね。文化祭や学生のイベントも盛んになっていてシンクロしていました。ああいうところはフラットな空間が基本デザインでしたから……。
今でこそヴェニューという語彙は比較的一般に使われるようになりましたが、もちろん当時の用語ではありません。規模の大小に関わらず、カテゴリー/分類/概念規定の難しい場所の総称として当たり前に使われるようになったのだと思います。つまり、新たに規定するのもヤボになる用語ですかね。簡単に言えば、なにかが起きる/起きている/起きた──場所や空間ということですね。同じ場所でもなにも起きていなければ単なる「place (場所)」ということになる。しかしそれは、あるコミュニティに属した意味において……ということですね。一般用語としては、犯罪現場も代表的ヴェニューなのが示唆的かも。
●「場所」は現場と化し物語を生むということですね。ボードレールの昔は「場所」が街路やアーケードであり殺人事件が起こり探偵小説が生まれる。それこそウラジミール・マヤコフスキーの「街路は絵筆で、広場はパレットだ」やチューリッヒ・ダダのフーゴ・バル「キャヴァレー・ヴォルテール」でも詩の朗読や小演劇が上演されていました。これらもヴェニューといえるのかも知れません。
それで今思い出しましたが、イス無しが「クラブ・モダーン」の特異な場所である要因のひとつですね。当時はそのような場所はなかった。その後のEP-4への流れも含めてそのような「場所」を必要と考えていることはよくわかりました。
さて、「クラブ・モダーン」じゃないけど「パームス」へは頻繁に行きました。佐藤さんとは韓国の政治状況について話した記憶もありますよ。読売TV『11PM』のロケも「パームス」の前でした。
その「パームス」で阿木さんと『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』の構想を練られたのでしょうか?
★ロック・マガジンの事務所には一度しか行ってないと思うので、パームス、もしくはその周辺でしょうか。京都で松岡正剛さんと会ったときに阿木さんもジョインしたりして、そんな折にふれた構想だったかと思います。
●最初『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』に関しては、佐藤さんから阿木さんに持ち込まれたのですか?それとも阿木さんからの依頼で提供したのでしょうか?
★いやあ、どっちということもなかったので記憶の彼方です。宅録ユニットでいくつか変なのがありますよ……ってことで阿木さんに聴いてもらってはいました。その中でもR.N.A. Organismというユニット名が気に入っていたようで、インフルエンザやウイルスについてその特異性、その音楽的相似性などについてああだこうだ徒然のうちにリリースが決まっていたんじゃなかったかな……。
●R.N.A. OrganismとしてなぜVanityからのリリースだったのでしょうか?
佐藤さんと阿木さんの間でどのような目的なり目論見があったのでしょうか?
★先ほどのヴェニューの話と同じように、作品化やそのメディア、レーベルなどは、DIYで音づくりを始めた人間には重要なテーマでしたから。当時は色々な人と多くの意見を交わしていました。実際には、本気で作品を世に問う気があるなら方法はいくらでもあり簡単なことだ……というのがぼくの立場でした。だから、その中のひとつがR.N.A. OrganismでありVanityだったということかな。
ぼくの立場としては、やってみたいことや、やれそうなことがR.N.A. Organismに限らず山積みになっていた時期で……。同時期には、のちに発売されるイーレムの『沫』(81年、R.N.A. Organismも参加)というLP2枚組コンピレーションの企画も始まっていましたし、カセット・レーベルのSkating Pearsも準備していたりだったので、特別な目論見みたいなものはぼくの側にはなかったと記憶しています。
●レコーディングはどのようにされたのでしょうか。他のVanityミュージシャンと同じようにスタジオ・サウンド・クリエーションなどのスタジオとか使われたのでしょうか?また阿木さんのプロデューサーとしての役割とはどのようなものだったのでしょう?
★京都の普段使っていたスタジオでメンバーとぼくだけで録ったものと、大阪のサウンド・クリエーションで阿木さんが加わって録ったものを合わせて進行しました。阿木さんはまあ……テクニカルなところが暗くて、変わったことをしようとすると説明に時間がかかったなあ。音楽プロデューサーとしてではなく、エグゼクティブ・プロデューサー(統括制作者)かレコード会社の担当ディレクターという感じで意見をもらいました。で、アルバムとして仕上げる段階の諸々決定は、メンバーとぼくの意見を参考に阿木さんのほうでまとめてもらうという役割でしたね。
●話は変わりますが、ひょっとして『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』のジャケット・デザインは佐藤さんが提案したものですか?なぜこんな質問をするかというと、それまでの物語性を持ったVanity Recordsのものとは全く違う無機質なミニマルなものに変わっていますよね。確かに雑誌をデザインする際にはインスタントレタリングを使ってはいましたが、レコード・ジャケット全面をインレタで被うとはちょっとびっくりしました。時系列で考えると1980年発刊の『fashion 1,2,3』の装丁では『ロック・マガジン』とは内容が違うとはいえ、裏表の表紙全面がR.N.A. Organismのジャケット と同様にインレタで覆われていました。
★そうですね。ぼくが考えていたものとは多少異なった結果になりましたが、記号インレタのシートをまんま使いましょうと提案して、いくつかサンプルを渡してアイデアを伝えました。インナースリーヴにもクレジットがあるように、デザインはメンバーとぼくで大凡を詰めて阿木さんに打診するというやりとりでした。確かR.N.A. Organismをリリースする話が始まった当初に、ジャケットの件やレコードのカッティングやプレスについてアイデアなどを伝えて諸々調べてもらいました。最終的デザインは統括の阿木さんにお任せすることになったんです。
その後、あのジャケットと同じ系列のデザインを阿木さんが好んで使うようになったのは知っています。まあ、阿木さんらしいという一貫性ですかね? ぼくとしては“オリジナル”なんてことを標榜するのは破廉恥だとしても、方法的懐疑を抜きに進めることはある種の原理に反して、同様に破廉恥なことだと……。
●いやあ、その破廉恥さがデザイナー阿木譲の才能だし他に類を見ない(笑)。感覚に触れたものを使って何が悪いってよく言ってました(笑)。
レコード・ジャケットは音楽の衣装を纏わす重要なものだと思いますが、阿木さんは「R.N.A. Organism」をブック・デザインに応用していったんですね。今remodelとしてBOXセットがリリースされていますが、『fashion』のデザインが踏襲されているのは感慨深いものがあります。
ところで、R.N.A. Organismの由来は?新型コロナ・ウイルスも「情報」としてのRNAを持っていますね。
名前に対する想いなどあれば教えてください。
★いまでも続いているウイルスは生物か否かという論争が由来だと思います。当時は、生物であるか否かは別としてもウイルスは生物進化に決定的な影響を及ぼしていることが明確になりつつあった時期で、メンバー間では〈DNAをもたない特異性生物〉という合意があったということです。それが自然にユニット名となったらしいです。78年の結成時だったか……。
●音楽はウイリアム・バローズがいうウイルスだと思いますし、連想させますよね、しかも密だし(笑)。
ところで『ロック・マガジン』とか読んでました?それともFAZZ BOX IN?
★はっきり言って読みものとしては読んでいませんでした。ほかでは紹介されないレコードの情報を得るための情報誌という感じでしたから、何号と言えるような読者じゃありませんね。FAZZ BOX INについても同様な番組としてエアチェックしてました。
●情報源としての『ロック・マガジン』ですか。僕の関わった頃の『ロック・マガジン』では如何に時代精神を表現するかということに重点を置いていたので、情報を流すというのは一義的には考えていなかったですね。
では当時聴いていた音楽は?叉影響を受けたアーティストやレーベルはありますか?
★あまりにも何でもかんでも聴いていたので……。オルタナ系は業務全般という感じで掘っていましたが、個人的な対象はブラジル~南米系とアフリカ系のヴァイナルでした。とにかく本場モノは入手困難な時代でしたから。それと、ブラック・ミュージックの流れから生じた辺境系。韓国歌謡/ロックにもはまっていた時期ですね。まあ、ブラインド・ディガーでしたが……。
●現在関心があるアーティストは?メチャクチャたくさん聴かれているとは思いますが、興味があります。当然φonon関連になると想定していますが、それ以外で注目しているミュージシャンについては?
★残念ながら物理的要因で積極的リスナーになれない状況がこの10年ほど続いています。必要火急を基本に対応していますので、φonon関連以外の外交上のやりとりや具体点について明らかにすることは控えさせていただきます……。
●やっぱり(笑)。そうですよね。
では質問を変えて(笑)、2020年の音楽をどのように読み取っていますか?ヴェイパー・ウェイブなどの動きも含めて、いかがでしょう。
★音楽だけではないのですが、メディアとしての体質的な問題というか、90年代後半以降、ネット前/後かも知れませんが、全体としてはすべてが等価で同時に存在し続けるような、末期的平坦風景が見えつつあるという気がします。情報の量と質ですべてが決定してしまうような、個人的パッションやらエモーションの介入する余地のないフラット性というか。どう発信/受信するか……、もちろん受信はリスナー側ですが、どのようにして出会った音で、それはどう聴かれるのかという神話的課題に誰もが知らずに対峙することになる。当然同じことが発信側にも生起するわけだし、双方の融合が顕在化したのが正に80年代、宅録以降のあの頃だったわけでしょ……。
当人は個人的パッション等々によって動機づけられているように思わせるメディア──、あまりにも何でもありなので自らよそ見をしないように調教されたメディア──、このブリンカー効果は当然受信側に強く発揮されますから、個々には平坦な世界は見えにくいようになっていく……。なっていくと言うより、自分でその仮想的な山あり谷あり世界/ストーリーを構築しちゃう。メディアというのは媒介ですから、そもそもその実体は存在しない仮想的なモノという本質が、ゆっくりと時間のかかる爆発を始めているんじゃないかと。フラットワールドに抗しがたいというストレスが、ヴェイパーウェイヴなどの形をとって表層化する。これはこれまでも/これからも繰り返されていることですが、それはどこまで持続性があるのかという疑問が重要な時期でしょうね。
●確かにメディアによるブリンカー効果という問題は大きいですね、受信者側が無意識的に自ら作り出していく錯覚はSF的世界にしかリアリティを感じないかも知れない。人と社会との関係性における現在の後期資本主義的社会をどのように感じていますか?またNet社会や次世代5Gなどの環境にどのように対峙しようとしていますか?
★なんちゅう質問ですか……。特になにも感じてないですよ!
ただレッテルというか概念については、後期資本主義やポスト資本主義というのは、あまりリアルではなくてロマンに感じてしまう。あるいはアンチ・ロマンか……。
単に資本主義というのであれば、概念の順序は別として熱力学的なエネルギー/熱量の問題を社会人類学的に置き換えたようなところがある。また私的所有や利益、競争原理となればダーウィニズムと支え合っているわけで、ある意味、資本主義の起源は人類誕生より古いシステムですよね。だからこそ本来は普遍的で、人類滅亡後も続いていくはずです。シンプルに言えば、そういう人間目線の収支、地球経済システムに帰結しちゃう。だとすれば、マルチな階層的インプットとアウトプットであっても、太陽エネルギー以外は等価な交換によってエントロピー増大を一時的に抑えるような、低エントロピーな仮想的定常状態をできるかぎり持続させるための運動なのかも知れない。ただ、そのスピードにおいて加速的に過ぎる資本主義に対する歯止めが必要だと考えることも自然で、★★主義や★★教という運動の骨子になり得るでしょう。
で、人間が人間抜きの思考を持てるかどうかは多いに疑問ではありますが、愛すべきノウアスフィアに端を発した生態学的思考の流れは、資本主義を含めた人類社会の実践的思考実験として注目かな……。アントロポセン/人新世~ホモ・デウスとソフィスティケートする潮流は、ソ連の仕掛けた時限装置の発動ではないでしょうか──って、マジに受け取らないでくださいね。でもまあ米国の大統領選挙を眺めていると、あながち軽口とも受け取ってほしくないですが……。
反対側には加速主義なんてのもあるわけで、つくづく人間は考えつくモノなら何でも考えるが、考えもつかないモノに関してはお手上げなんだと考えてしまうわけです。こんなんでいいでしょうか?
で、質問の連続性にも疑問がありますが……、いまとなってはネット社会やその環境の進化には特段大きなパラダイムの変換は必要ないかと思います。音楽の発信や受信への興味は尽きないけれど、配信方法はあまり気にもせず是々非々対応が無難というところ。その意味では、レーベル運営をある程度持続するためにはプラグマティックにならざるを得ないかな。
●現在の活動と今後の活動のプランを教えてください。
★現在も、近い今後もφononレーベルの運営が中心となる活動ですね。一身上の都合ということもあって、引きこもってCOVID対応で作業できるよう心がけています。
●これからの音楽芸術はどのようになってくると思いますか?また音楽を制作するにあたりどのようなことを考えていますか?佐藤さんにとって音楽とは?
★音楽芸術とは言えないかもですが、好みや傾向によってその場でAI生成されるものになるでしょうね。著作権の概念がどこまで持続するかわかりませんが、抵触しない音楽生成ということになるかな。生成~再生され、その場で消滅していくような。だから、音楽制作は音源提供という側面がはっきりしてくるんじゃないかな。最大公約数から提供される音ってことは、現在のヒット曲と大差ないアイデアだけれど、どうなるかは御慰みです。なんかフニャっとしたモノか……。
●「フニャっとしたモノ」、いいですね。情報処理技術の中ではRPAとか含めAI活用が現実の世界で眼に見えるようになって来てますね。それらの技術が、フニャっとしたほどほどで身の丈にあったもののために応用されればいいと思います。
さて最後の質問です。新型コロナ・ウイルス=パンデミックの同時代に対してどのような感想をお持ちでしょうか?生きている間にこのような時代(世界が民族や言語を超えて同時に同じ惨禍にある)と対峙することは、幸運にも(失礼)そうあることではありません。
★まだほとんどなにもはっきりしていないモノに対する、権威やシステムそして自分を含めた人間の反応に興味は尽きませんね。訳知りな言説や予言めいた物言いを含め、見えないモノを見ようとする/見てしまった人間が自ら背負った十字架のような……。先ほどのブリンカー効果と同じことですが、見えないことの恐怖から発生する集中と慣れ──、同時に、見えすぎることに対する反応にも留意しなければいけないかな。
●フニャっとしていてほどほどで身の丈にあった生き方を注意深くということでしょうか。
今回は佐藤さんと話が出来て嬉しかったです。ありがとうございました。
==========================================

★インタビューを終わって
確信を持てない修正第十二仮想記憶条項だらけの当時のトピックの中では、レコードという形で残すことができたR.N.A. Organismの存在は比較的記憶にはっきり焼き付けられている方だが、やはり細かな事情となると「???」な部分が多い。嘉ノ海さんに突っついてもらって少しずつ絞りだしてみたものの、実際に阿木さんやVanityに紐付けられているのは、それそのものより田中浩一さんや嘉ノ海さんをはじめとした人物の周縁事象だ。インタビュー中では触れなかったが、殊に、足穂の磯巾着に倣って「人類海鼠説」を称えた田中浩一は、原罪による世界の滅亡(二十五世紀的悲劇?)と人間以降を予見しながら高校の教壇に立っていたという大丈夫の魂だが、ある意味で不器用だった阿木さんの本質的な態様を彼こそが体現していたのだと感じている。
阿木さんにはなにかと僻事がつきまとい、会うたびに徒事を吐く五月蠅い男だと煙たがられていたと思う。ただ、自分とはまるで重ならない素性を面白がってくれていた気がする。もう少し言っておくべき事柄が残ってはいたが、いまに至れば術ないだけなので、ついでに尚更、煙になっておきたい。
●インタビューを終わって
佐藤さんとは当時はもちろん面識もあり話したこともあったのだが、阿木さんとの関係とか佐藤さんが何を考えていたのかなど知らないことばかりだった。R.N.A. Organismのことを中心にお伺いしようと思っていたが、時代の沫だったこともわかった。それより何よりも佐藤さんが試みていたことは「場所」を確保しようとしていたことだった。人が集まる場所、退避する場所、何かが起こる予感を帯びた場所。場所を模索し続けたのではと感じた。阿木さんも『ロック・マガジン』の後にM2(Mathematic Modern)や(nu things)、(environment 0g [zero-gauge] )を立ち上げて、ヴェニュー(場所)から外へと続くアヴェニュー(街路)へという想いがあったのではないかと想像した。
阿木さんと最後に会った時に「嘉ノ海、元気にしているのか、そろそろ何かを始めないといけないんじゃないか。」という言葉を思い出した。今も0gは場所から街路へと繋がっている。
==========================================

《今回リリースされたR.N.A. Organismの未発表ミックス集『Unaffected Mixes』を聴いて》
●全く別物ですね。びっくりしたと同時にほほーって、こう来たかと思いました。
当時のものの価値(R.N.A.O Meets P.O.P.O)は、時代は常に変化しているので当価値ではありません。
今回の「Unaffected Mixes」は、意匠を変えてというか、時代の「衣装」を着せ替えたものと理解しました。
特に最終曲終盤の残響(reverberation)音は、減衰していく音の波が見えるようでした。
今風の言い方をすると後期資本主義的世界(マーク・フィッシャー)の黄昏ていく風景への憧憬や祈りのようなものを感じました。少し先の歴史性へに対する感覚も。
★R.N.A. Organismの『Unaffected Mixes』は、カセットコピーした仮ミックスなどからテープの切り貼り編集などで制作していた当時のものです。阿木さんが、ライヴできるバンドというかユニットを望んでいてストレートなミックスが好みだったようなのであまり興味を示さなかったものです。一応ヴァニティ音源なのでいままで表に出さずにいたテープがけっこうな量ありますので、そこからセレクトしたもの。まだアルバム2~3枚分はあります。機会があれば他のトラックも放出したいと思います。有り体に言うとボツテイク集ということですが……。
●もちろん全体の雰囲気やメロディから当時のものだとわかります。タイトルも伊/仏語に変わっていたり、Singularなんて今風の言葉が使われていたりしてます。「全く別物ですね」は、Mixにより生まれ変わったといった意味です。加えて他のものも何らかの形で、是非リリースして欲しいです。
==========================================
VANITY0006『R.N.A.O Meet P.O.P.O/RNA ORGANISM』1980/05
佐藤薫の初期プロデュース作品。
”R.N.A. Organism”の一番初めの出現は、Vanity Recordsのミュージシャンが多く出演した1979年12月のロックマガジン主催のイベント「NEW PICNIC TIME」の匿名の観客としてだった。
頭髪を緑色に染めた集団。それは佐藤薫率いる時代に拮抗した過激派であり他の観客を刺激した。
当時佐藤薫が主宰(拠点?)していた京都河原町のディスコ「クラブ・モダーン」では、ダンスミュージックとして西アフリカの民族音楽をかけていた。何の加工もせずそのままの音源でリスナー(参加者)は朝まで踊っていた。
その「場所」は僕らが名付けたエスノ(エスノミュージックとテクノとを融合した)ミュージックの実験空間でもあったのだ。当然エスノにはジェイムズ・ブラウンなどのR&B、イヌイットの狩猟の音楽、日本の舞楽なども含まれていた。
イギリスでは”THE POP GROUP”や”THE SLITS”の音楽が新しい原始リズムを刻んでいた。二十世紀初頭ロシアの作曲家イゴーリ・ストラヴィンスキーの”春の祭典”のように…。
佐藤薫は現在も時代精神を反映した個人レーベル「フォノン」で時代の響き(ドローン)を発信し続けている。二十一世紀音楽は「響き」をいかに時代の背景音として捉えるかにかかっている。現在の彼の音楽的冒険はいわば二十一世紀にメタモルフォーズし再登場したパンクミュージックだ。
【Vanity Recordsと『ロック・マガジン』1978-1981より】
